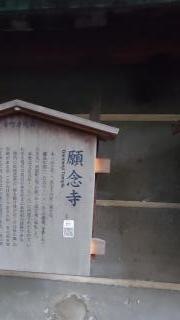「ホテル金沢」から直線距離で半径3km以内の神社・寺院を探す/距離が近い順 (1~98施設)
①施設までの距離は直線距離となります。目安としてご活用ください。
②また ボタンをクリックするとホテル金沢から目的施設までの徒歩経路を検索できます。
ボタンをクリックするとホテル金沢から目的施設までの徒歩経路を検索できます。
-
-

-

- 0枚
-
-

-

- 0本
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 金沢市東御影町に鎮座する豊国神社は、歴史と文化の息づく神社です。この神社は、日本の戦国時代を代表する名将、豊臣秀吉を御祭神として祀っており、加賀百万石の城下町として栄えた金沢における歴史的、文化的な存在として知られています。 豊国神社の創建は、江戸時代の初め、1625年(寛永2年)に遡ります。この神社は、豊臣秀吉の死後、その功績を讃えるために建てられたものです。秀吉は日本統一を成し遂げた偉大な人物であり、彼の名を冠する豊国神社は、全国各地に存在していますがその中でも金沢市の豊国神社は、加賀藩の藩主前田家との深い関わりが特徴です。 豊臣秀吉と前田利家は親しい関係にあり、利家は秀吉の側近として重要な役割を果たしました。利家の死後、前田家は徳川幕府に従う形で生き残りを図りますが、秀吉への恩義を忘れることはなかったと言われています。これらの背景のもと、豊国神社は秀吉の功績を称える場として、また前田家の忠誠を象徴する場所とし設けたものとされています。 豊国神社の境内は静寂に包まれており、訪れる人々に落ち着いた雰囲気を提供します。鳥居をくぐると、石畳の参道が続き、その先には本殿が鎮座しています。本殿は伝統的な木造建築で、細部にわたって精緻な装飾が施されています。 また、秀吉の功績を記念する石碑や銅像があり、訪問者が彼の偉業に思いを馳せることができます。 豊国神社で5月に行われる「豊国祭」では、地域住民が参加して神輿や山車を担ぎ、町中を練り歩きます。また、豊臣秀吉にまつわる歴史劇の上演や地元の伝統芸能の披露など、豊国神社ならではの文化的なイベントも開催されます。 豊国神社は、商売繁盛や開運の神社としても知られており、お正月の初詣では新年の祈願を行う多くの参拝者で賑わいます。 神社周辺には金沢の伝統的な工芸品や和菓子を楽しめる店も多く、参拝後に金沢らしい文化を堪能することができます。特に、神社で授与される御朱印は、観光客に人気のアイテムです。秀吉を象徴するデザインが施された御朱印は、訪れた記念として最適です。金沢にお越しの際には参拝し、御朱印をいただいてはいかがでしょうか。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 昨年の秋に、金沢へ旅行に行った際、どこかおすすめの観光地はないかな、とネットで検索していたところ、この妙立寺を見つけました。 別名「忍者寺」と言われているそうで、落とし穴になるお賽銭箱や、隠し階段などがあるとのこと。 それを読んだ瞬間、楽しそう!!行ってみたい!と思いました。 事前に予約が必要とのことで、電話をかけたら希望の日時に無事に予約ができました! 当日は旅行の2日目、偶然にも金沢マラソンと重なっており、市内は交通規制がかかっていました。 バスなどが運休している時間もあり、妙立寺に行けない!!!どうしよう!?とちょっと焦りましたよー。 そこで、タクシーを利用して行くことにしました。 タクシーの運転手さんが、規制がかかっていないところを通って、妙立寺まで連れて行ってくださり、予約していた時間よりも早く到着することができました。 予約の時間より30分以上早く到着したのですが、お寺の案内の方に名前と予約していることを伝えると、ひとつ前の予約の枠に入れてくださいました。 ありがたかったです! まずは本堂に入り、お寺の説明を聞きます。 十数人ほどのグループになり、案内の方の説明を聞きながら堂内を進んでいきます。 堂内では撮影が禁止だったので、いろいろな「しかけ」の写真はないのですが おどろくことばかりで、とっても楽しかったです。 お寺の外観は2階建てなのですが、なんと内部は4階建てで7層からなっているというのですから、なんとも不思議です。迷路のようになっていましたよ。 当時は3階建て以上の建物は禁止されていたそうで、外からは2階建てにしか見えないようにしていたみたいです。 物置の戸を開いて、床板をまくると階段がでてきて、その中に人が身を隠すことができるようになっていたり、渡り廊下に見せた階段で、床板をはずすと落とし穴になっていたりと、あちらこちらにたくさんのしかけがいっぱいでした! 本堂の正面入り口にあるお賽銭箱は、落とし穴としても利用できたそうです。 伝説の井戸は深さ25Mほどあるそうです。茶水に利用されていましたが、水面に横穴があり、それが金沢城まで続いていて、逃げ道になったとも言われているとか! 昔の方の知恵は本当にすごいですね! とっても楽しかったし、みなさんにもおすすめしたい観光スポットです。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 石川県金沢市の野町にあるお寺で、自分が現在居住している町の隣町にあります。最近拝観したのですが、自分の住んでいる近くに日本の歴史上の出来事に大きく関わったお寺がある事を改めて知り驚いています。三光寺については、明治11年(1878)、大久保利通を東京の紀尾井町で暗殺した島田一良たちの集会所であったとして有名なお寺です。そのため事件の首謀者たちは「三光寺派」と呼ばれました。その歴史は古く、創建されたのは、1635(寛永12)年に創建されました。山門は平成3年(1991)に石の仁王門として現住職自ら制作し再建されました。また、現住職彫刻の石の仁王門は必見。境内には水琴窟もあり、いつでも聞くことが出来て、その清々しいい音色に魅了されます。アクセス方法は、JRで来られた方は金沢駅からバスで15分 北陸鉄道路線バス、城下まち金沢周遊バスを利用してもらい広小路バス停から徒歩で3分になります。金沢市内を走る「ふらっとバス」を利用の場合は、武蔵ヶ辻・近江町バス停からバスで25分 金沢ふらっとバス長町ルートに乗り野町広小路バス停から徒歩で4分の場所になります。金沢在住の私でも、最近になって訪れた場所ですので、観光でお越しの際は、一度散策してみても良いかと思います・
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 石川県金沢市寺町にあるお寺で通称「大桜」と言われ地元住民に親しまれています。自宅から近く歩いてゆける距離にあるので、桜の季節には子供たちが小さい時に、家族で散策に出かけた思い出があります。町の名前「寺町」の通り、近隣には寺院群があり多くのお寺が立ち並んでいます。車でアクセス方法は、金沢市の中心を取る野田専光寺線を広小路交差点より野田方面へ向かって、懐石料理で有名な料亭の「つば甚」の迎いになります。公共交通機関のバスを使用する場合は、野町広小路バス停より徒歩で約5分に位置になります。松月寺が創建されたのは文禄2年(西暦1593年)になります。改ざんした師は「大安存察大和尚」、開基は「瑞亀院殿夕雲全劫居士」、ご本尊は「釈迦牟尼仏」、現在のご住職は「槻 健二さん」になります。お寺の特徴としては、先にも書きましたが、毎月4月中旬には大桜が満開になり、見頃となります。平成15年には、石川県農林試験場によって育てられた大桜直系の若木を大切に育て後継木として育てています。大木の根の周囲は約6m、高さ約14mもあり、お花の大きさが約5cmの美しい白いお花を咲かせます。お寺の文化財としての評価は、昭和18年8月に国の天然記念物の指定を受けています。この桜は加賀藩3代藩主前田利常と親しい仲であった松月寺2世至岸和尚が小松城から大切に持って来て移植した桜であるとの事です。大桜は学名をショウゲツザクラといい、ヤマザクラ・オオシマザクラ系の一種で学名にお寺の名前が付く由緒ある桜であることが伺えます。お寺が創建されたのは、先にも書きました通り、文禄2年(1593年)に越前堀井庄に於いて創建されました。その後、金沢、富山、金沢市の小立野台へと転々とし、元和元年(1615年)に現在地に移転したと歴史書には書かれています。境内には樹齢約400年の桜の木が大通りへはみ出し、大桜として親しまれている為、桜の季節には特に目に入り、地元の人たちはもちろんですが、多くの観光客の方々が来観されています。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 石川県金沢市の寺町寺院群にあるお寺になります。伏見寺は石川県金沢市寺町5丁目にある高野山真言宗の寺院になります。伏見寺の創建年度は不詳ですが言い伝えによると西暦717年(養老元年)、芋掘藤五郎が寺院を建立し採掘した砂金で制作した本尊となる阿弥陀如来像に、行脚でたまたま当地を訪れた行基菩薩(奈良時代の高僧)が開眼供養したのが始まりと伝えられています。当初、伏見寺は今の金沢市南部になる石川郡山科村にあったとの事です。その後、1615年(元和元年)に快存和尚が現在地である寺町に移しているとの事です。本尊に祭られてある阿弥陀如来像は平安時代初期に制作されたもので銅造鍍金像、像高22.1㎝、平安時代の金銅仏の遺構として大変貴重な事から1950年(昭和25年)に国指定重要文化財に指定されています。伏見寺の護摩堂に安置されている木造不動明王坐像は平安時代に制作されたもので一木造、2014年(平成26年)に金沢市指定文化財に指定されています。伏見寺は金沢の地名の起こりとなったとされ境内には芋掘藤五郎のものと伝わる墓碑が建立されています。歴史に興味にある方は、是非とも金沢の地名の由来となったこのお寺で、芋ほり藤五郎の歴史に触れてみるのは如何でしょうか。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 石川県金沢市に佇む宝円寺(ほうえんじ)は、歴史と美しさが融合した立派な寺院です。特に前田利家ゆかりの寺として知られ、その由来や歴史、美しいまつりなどが観光客や信仰者に訪れる魅力となっています。先日初めて訪れることが出来て、少しお寺に纏わることを調べることが出来ましたので、宝円寺の歴史と由来、美しいまつり、アクセスについて紹介したいと思います。宝円寺は、江戸時代初期の慶長年間(1596年 - 1615年)に、前田利家の嫡男である前田秀次によって創建されました。秀次は前田利長の兄として生まれ、金沢藩初代藩主前田利長の異母兄弟として知られています。寺の建立は、前田利家の菩提を弔うとともに、藩政の安泰を祈るために行われました。宝円寺の名前には、「宝(ほう)」は財宝や幸福を、「円(えん)」は円満や安定を意味し、これらの願いが込められています。寺の境内には、利家や秀次の位牌が祀られており、前田家ゆかりの霊を尊んでいます。宝円寺では、毎年春になると「宝円寺お祭り」が行われます。これは、寺の境内や周辺地域で様々な催し物が行われ、地元住民や観光客で賑わいます。特に美しい行列や伝統的な祭りの要素が組み込まれており、見どころ満載です。お祭りでは、華やかな神輿渡御や舞踏、伝統的な装束を身にまとった参加者たちの行進が、歴史と宗教の雰囲気を堪能できる一大イベントとなっています。宝円寺へのアクセスは、金沢市内からも比較的アクセスが良好です。市内中心部からは車やバスを利用して、20分ほどで到着することができます。宝円寺はその歴史や宗教的な要素だけでなく、美しいまつりや年中行事などが組み合わさり、観光地としても魅力的です。境内には季節ごとに美しい自然や庭園が広がり、参拝客や散策客に心地よいひとときを提供しています。宝円寺は金沢市の歴史的な寺院であり、前田利家ゆかりの場所として親しまれています。歴史と宗教、美しいまつりなどが融合し、訪れる人々に静かなる時間と感動をもたらします。信仰の場としてだけでなく、観光地としてもぜひ訪れてみる価値がある場所だと思いますので一度足を運んでみては如何でしょうか。
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本