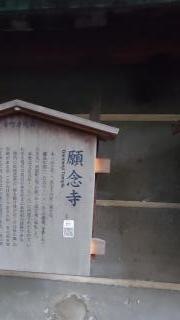「ホテル金沢」から直線距離で半径3km以内の観光スポット・旅行・レジャーを探す/距離が近い順 (1~140施設)
①施設までの距離は直線距離となります。目安としてご活用ください。
②また ボタンをクリックするとホテル金沢から目的施設までの徒歩経路を検索できます。
ボタンをクリックするとホテル金沢から目的施設までの徒歩経路を検索できます。
-
周辺施設ホテル金沢から下記の店舗まで直線距離で1,508m
HIS アバンティ&オアシス金沢店/ HIS185店舗
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 石川県唯一のHISです。金沢の香林坊にあります。バス停は香林坊の日銀前とアトリオ前が近いです。車でお越しの際は近くのコインパーキングに停めていただくことになります。いつも入店したらすぐに声を掛けてもらえます。私は女性の方が担当でしたが、好感の持てる対応で是非またお願いしたいと思いました。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 金沢百万石まつりです。昔からある、金沢の伝統あるお祭りです。主なイベントはさまざまな出し物で長い行列になって金沢の街を歩きます。毎年有名人が前田利家やお松の方などを演じます。馬に乗りながら行列を歩きます。私は、小学校の頃に加賀梯子登りで参加したことがあります。私の役目は梯子を支えたりします。私の父と妹は梯子を登っていました。梯子はさまざまな演目が決まっており、それを披露します。長い距離を歩くので小学生のわたしは結構疲れましたがいい思い出です。小学校四年生から六年生まで三年間参加させてもらいました。加賀梯子登りだけでなく、吹奏楽部の演奏や踊りがあります。老若男女、みんなが毎年楽しみにしているお祭りで、金沢で一番盛り上がります。6月の第一土曜日と日曜日に主にしていると思います。金沢にくるタイミングが合いましたら、是非参加してみてはいかがでしょうか。屋台などもたくさん出ており、とても楽しいです。
-
周辺施設ホテル金沢から下記の施設まで直線距離で1,602m
金沢グレイスチャペル
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 金沢グレイスチャペル、結婚式やお祝いにも会場をお貸ししている教会でその神秘的で清らかな空間に誰もが圧倒されます。 また懺悔の儀も執り行われており、贖罪の念に駆られる罪を背負い生きる人もまたこの地に訪れることもあるそうです。願わくば良き導きと加護を授かれるかもしれません。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- JTB香林坊大和店は香林坊大和の7階にあります。先日JCB商品券購入の為に寄ると従業員の方が丁寧に対応してくれました。接客も好感持てましたが従業員の方がアロハシャツを着ていたのを見て気持ちが和みました。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 先日、東京から大学時代の友人が出張で金沢に来るという事で、一緒に観光で訪れた資料館を紹介します。金沢市の中心に位置する前田土佐守家資料館は、日本の歴史と文化を伝える重要な施設の一つです。この資料館は、加賀藩の歴史や前田家に関する貴重な展示物を収蔵しています。これから前田土佐守家資料館の展示物や概要、収蔵品、観光客への魅力、歴史的背景、金沢市や加賀藩の関連性、催事や講座についてご紹介したいと思います。資料館では加賀藩の武士の武具や、前田家の家宝として受け継がれた刀剣や、前田家に関する書画や史料、家訓、書簡などが展示されています。これらは加賀藩の歴史や前田家の家族関係を理解する上で重要な資料となっています。また、前田家の日常生活や文化に関する展示もあり、茶道具や調度品などが展示され、資料館自体が歴史的建造物として価値があり、その建築様式や歴史的背景も展示されています。前田土佐守家資料館は、観光客にとって魅力的なスポットの一つです。加賀藩の歴史や前田家に関心のある人々にとって、ここは必見の場所となっています。また、日本の武士道や武士文化に興味を持つ人々にとっても、貴重な情報源になると思います。前田土佐守家は、加賀藩の有力な家臣団の一つであり、金沢市を中心とする加賀藩の政治や文化に重要な影響を与えました。加賀藩は、戦国時代から江戸時代初期にかけて栄えた歴史的な藩であり、その文化や歴史は金沢市に色濃く残っています。前田土佐守家資料館では、定期的に催事や講座が開催されています。これには、加賀藩や前田家に関する特別展示や講演会、ワークショップなどが含まれます。これらの催事や講座は、一般市民や観光客が加賀藩や前田家の歴史をより深く理解し、その魅力に触れる機会を提供しています。前田土佐守家資料館は、日本の歴史と文化を伝える重要な施設であり、金沢市や加賀藩の歴史を理解する上で貴重な資料となっています。観光客や歴史愛好家にとって、訪れる価値のある場所です。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 神社仏閣めぐりを50歳を過ぎてから趣味としている、石川県金沢市在住のわたしが、金沢にすみながらまだ一度も伺った事が無かったので先日散策してきたので、ご紹介します。このお寺の創建は、日蓮宗妙具山全性寺は室町時代の大永2年(西暦1522年) 北国身延とも称せられた越前脇本の妙泰寺住職、本妙院日仁上人によって、越中放生津(富山県新湊市)に創建され歴史的には500年の歳月が経ち今に至ります。境内にある案内看板には、天正年間(西暦1573年~1593年)になり 前田利家の長男で加賀藩初代藩主の前田利長に従い、富山、越中守山(高岡)、そして金沢に寺庵を移し、天明6年(西暦1786年) 現在地である金沢市の東山寺院群に移ったとの事です。不幸なことに宝暦9年4月(西暦1759年)、および明和8年2月(西暦1771年) の大火によって本堂、庫裡を類焼し、寺宝等を焼失したため、全性寺に関する詳しい資料が現在まで残っていないとの事でした。全性寺を巡る上で非常に有名なのが、その山門になります。この山門は、楼門(ろうもん)と呼ばれる2階建ての門の形式のひとつで、2階に縁側を廻し、高欄を設けるのが特徴です。細かい説明として建物様式は木部をベンガラ塗りとし、2階建てで、入母屋造(いりもやづくり)の屋根とした風格のある外観になり、金沢でもこの地区のシンボル的な存在であり、「赤門」の愛称で広く金沢市民に親しまれています。さらに深掘りすると 細部様式から、18世紀後半に建てられたと推定されます。正面の柱間を三間(さんげん)とし、中央間に扉を1箇所設けた楼門を三間一戸楼門(さんげんいっころうもん)といい、この形式とする現存する門として金沢市内で唯一のもので見ていてもその荘厳さは圧巻です。もちろん、金沢市指定文化財であり種別は有形文化財建造物として平成16年1月21日に指定されています。アクセス方法として車でお越しの際は、北陸自動車道金沢東ICから約15分(約5Km) 、公共交通機関利用の場合は金沢駅東口から鳴和方面行路線バスに乗車し森山バス停下車、徒歩2分の場所になります。境内の拝観料が無料で駐車場も近隣を利用できるので、金沢にお越しの際は是非拝観して欲しいお寺です。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 金沢城を訪れた際の感想は、その壮麗さと歴史の深さに圧倒され、まるで時代を超えた旅をしているような気分になったことです。金沢城は、加賀藩の藩主であった前田家の居城で、江戸時代の城郭建築の美しさとともに、加賀藩の歴史的な背景が色濃く反映されています。城の敷地に足を踏み入れると、まずその規模の大きさに驚きましたが、それだけでなく、城の建物や庭園の造形に込められた細やかな技術や、歴史の重みを感じることができました。 金沢城は、特にその「石垣」の美しさで有名です。石垣はその構造が非常に堅固で、しかも美しく積まれており、加賀藩がいかにして国の安定と威厳を象徴しようとしたかがうかがえます。石垣の上に立って遠くを眺めると、金沢市内が一望でき、その景色はとても壮大でした。天守閣は現在再建されておらず、その代わりに「三十間長屋」や「菱櫓」などの城郭建築が見ることができますが、これらの建物もまた見応えがあります。特に「三十間長屋」の建物は、非常に長く、長屋の中にある様々な部屋の配置やその建材の美しさに感心しました。 城内には、かつての武士たちが使ったと思われる武具や道具の展示もあり、当時の生活や文化を垣間見ることができます。展示品の一つ一つには、細かな説明が付けられていて、訪れる人がその背景や歴史を理解しやすくなっています。特に印象に残ったのは、加賀藩の家紋や、藩主が使っていたと思われる装飾品や日用品で、それらを通して藩主や城を支えた武士たちの暮らしを感じることができました。 また、金沢城はその庭園にも特徴があります。「城内庭園」や「玉泉院丸庭園」など、手入れの行き届いた庭園が美しく、静かな空間が広がっています。玉泉院丸庭園は、特に池泉回遊式庭園として有名で、池を中心に整備された緑豊かな庭は、四季折々に異なる顔を見せてくれるので、何度訪れても楽しめそうです。池に映る木々や、季節ごとの花々が庭園の中に色を加え、心を和ませてくれました。 金沢城の敷地内にはまた、武家屋敷跡や土塀なども残っており、城周辺の街並みも観光スポットとして人気です。街を歩くと、江戸時代にタイムスリップしたかのような気分になり、武士たちの暮らしぶりや、城下町の様子を想像しながら歩くことができます。特に「城下町金沢」の雰囲気を感じることができ、周囲の建物や道路の配置も、当時の名残が色濃く残っていることが感じられました。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 神社仏閣めぐりを50歳を過ぎてから趣味としている、石川県金沢市在住のわたしが、金沢にすみながらまだ一度も伺った事が無かったので先日散策してきたので、ご紹介します。このお寺の創建は、日蓮宗妙具山全性寺は室町時代の大永2年(西暦1522年) 北国身延とも称せられた越前脇本の妙泰寺住職、本妙院日仁上人によって、越中放生津(富山県新湊市)に創建され歴史的には500年の歳月が経ち今に至ります。境内にある案内看板には、天正年間(西暦1573年~1593年)になり 前田利家の長男で加賀藩初代藩主の前田利長に従い、富山、越中守山(高岡)、そして金沢に寺庵を移し、天明6年(西暦1786年) 現在地である金沢市の東山寺院群に移ったとの事です。不幸なことに宝暦9年4月(西暦1759年)、および明和8年2月(西暦1771年) の大火によって本堂、庫裡を類焼し、寺宝等を焼失したため、全性寺に関する詳しい資料が現在まで残っていないとの事でした。全性寺を巡る上で非常に有名なのが、その山門になります。この山門は、楼門(ろうもん)と呼ばれる2階建ての門の形式のひとつで、2階に縁側を廻し、高欄を設けるのが特徴です。細かい説明として建物様式は木部をベンガラ塗りとし、2階建てで、入母屋造(いりもやづくり)の屋根とした風格のある外観になり、金沢でもこの地区のシンボル的な存在であり、「赤門」の愛称で広く金沢市民に親しまれています。さらに深掘りすると 細部様式から、18世紀後半に建てられたと推定されます。正面の柱間を三間(さんげん)とし、中央間に扉を1箇所設けた楼門を三間一戸楼門(さんげんいっころうもん)といい、この形式とする現存する門として金沢市内で唯一のもので見ていてもその荘厳さは圧巻です。もちろん、金沢市指定文化財であり種別は有形文化財建造物として平成16年1月21日に指定されています。アクセス方法として車でお越しの際は、北陸自動車道金沢東ICから約15分(約5Km) 、公共交通機関利用の場合は金沢駅東口から鳴和方面行路線バスに乗車し森山バス停下車、徒歩2分の場所になります。境内の拝観料が無料で駐車場も近隣を利用できるので、金沢にお越しの際は是非拝観して欲しいお寺です。
-
卯辰山望湖台
所在地: 〒920-0833 石川県金沢市末広町
- アクセス:
「「望湖台」バス停留所」から「卯辰山望湖台」まで 徒歩3分
北陸自動車道「金沢東IC」から「卯辰山望湖台」まで 3.9km
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 先日、久しぶりに妻とドライブしたときに立ち寄った思い出の場所です。結婚する前に、何度かデートで訪れた場所で、食事をした後に夜景を楽しんだのを思い出します。そんな、卯辰山望湖台の魅力やデートでの楽しみ方、眺望の素晴らしさについて少しご紹介します。卯辰山望湖台は、石川県金沢市に位置する素晴らしい観光地で、その名の通り美しい湖の景色を一望できる絶景ポイントとして知られています。デートや観光に訪れる人々にとって、魅力的なスポットとして広く親しまれています。卯辰山望湖台は、標高約240メートルに位置し、金沢市街や近くに広がる湖の美しい風景を見渡すことができます。特に夜景は圧巻で、点々と灯りが灯った金沢市街が幻想的に輝き、デートに最適な雰囲気を演出してくれます。昼夜を問わず、見晴らしの良さが訪れる人々を魅了しています。卯辰山望湖台からは、湖面に広がる景色が一望できます。季節ごとに変化する湖の表情は、桜が咲き誇る春、緑に包まれる夏、紅葉が広がる秋、雪化粧した冬と、四季折々の風景が楽しめるため、何度訪れても飽きることがなく、そのロマンチックな雰囲気からデートにぴったりのスポットとして人気があります。夕暮れ時になると、夕陽が湖面に映り、優雅で美しい夕景が広がり、デートやカップルの特別な日に訪れ、夜景や星空を眺めながら、心温まる時間を過ごすことができます。近くにはデートスポットとしても有名な飲食店が多く、夜景を観ながらデートをする利用客が多く、私も現在の妻と一緒に、若い頃何度かデートで訪れたことを思い出します。卯辰山望湖台へのアクセスは非常に良好で、車でのアクセスが便利で、周辺には駐車場があり、車を停めて気軽に観光を楽しむことができます。また、公共交通機関も利用可能で、バスやタクシーを利用することで手軽に訪れることができます。季節ごとに異なる風景が楽しめるため、訪れるタイミングによって様々な魅力が堪能できます。春には新緑、夏には涼やかな風、秋には紅葉、冬には雪景色と、四季それぞれの風情を味わえることが、この場所の大きな特長となっています。金沢市内からアクセスが良く、その見晴らしの良さやデートにぴったりの雰囲気から、地元の人々だけでなく観光客にも愛されています。四季折々の美しい自然と眺望の素晴らしさを楽しみながら、特別なひとときを過ごすならば、卯辰山望湖台は最適な選択と言えるでしょう。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- コロナ禍でのマスクの着用も緩和され、久しぶりに家族で金沢散策のドライブに出かけた時に、立ち寄ったのが「金沢くらしの博物館」になります。生まれも育ちも金沢ですが、灯台下暗しと言いますか、今まで一度も行った事が無かったので金沢の近代史を知る上で新鮮な気分になりました。「金沢くらしの博物館」は、江戸時代から現代までの金沢市民の生活や文化を展示する博物館です。金沢で有名な兼六園などの観光スポットから徒歩圏内です。また、市内中心部からもバスや車でアクセスが可能です。博物館の中には、江戸時代から現代までの金沢市民の生活や文化をテーマにした展示があります。主に民具・生活用品・日用品・伝統文化など、金沢の生活に関する様々な展示物があり、特に、江戸時代に金沢市が発展した背景や、金沢市民の生活や文化についての展示は興味深く、歴史や文化に興味のある方にはおすすめです。また、博物館には、金沢市民が使ってきた生活用品や日用品、祭りで使われる民具や装飾品などが展示されています。 その他にも、金沢の伝統工芸品である金箔や漆器、工芸品展示物の中には、金沢市民の生活や文化に関するものだけでなく、石川県全体や日本の文化についての展示物もあるため、金沢市に滞在する方には、地元の文化を知る良い機会になると思います。博物館の中には、金沢市の歴史や文化について学べる体験型の展示もあり館内にいたお子様連れの親御さんもすごく楽しんでいる姿が印象的でした。金沢市民が使用していた民具や生活用品の他にも、踊りや演劇、音楽など、金沢市の伝統文化を体験できるコーナーもあり楽しめる施設になっています。また、展示物を見ながら、音声ガイドやパンフレットで詳しい解説を聞くこともできます。博物館の中には、カフェやショップも併設されていて、カフェでは、地元の食材を使ったメニューが提供されており、金沢の美味しい食べ物を味わうことができます。今まで、訪れる機会が無かったので非常に楽しめる施設が近くにあることを知り満足感にあふれる金沢散策になりました。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 石川県金沢市に佇む宝円寺(ほうえんじ)は、歴史と美しさが融合した立派な寺院です。特に前田利家ゆかりの寺として知られ、その由来や歴史、美しいまつりなどが観光客や信仰者に訪れる魅力となっています。先日初めて訪れることが出来て、少しお寺に纏わることを調べることが出来ましたので、宝円寺の歴史と由来、美しいまつり、アクセスについて紹介したいと思います。宝円寺は、江戸時代初期の慶長年間(1596年 - 1615年)に、前田利家の嫡男である前田秀次によって創建されました。秀次は前田利長の兄として生まれ、金沢藩初代藩主前田利長の異母兄弟として知られています。寺の建立は、前田利家の菩提を弔うとともに、藩政の安泰を祈るために行われました。宝円寺の名前には、「宝(ほう)」は財宝や幸福を、「円(えん)」は円満や安定を意味し、これらの願いが込められています。寺の境内には、利家や秀次の位牌が祀られており、前田家ゆかりの霊を尊んでいます。宝円寺では、毎年春になると「宝円寺お祭り」が行われます。これは、寺の境内や周辺地域で様々な催し物が行われ、地元住民や観光客で賑わいます。特に美しい行列や伝統的な祭りの要素が組み込まれており、見どころ満載です。お祭りでは、華やかな神輿渡御や舞踏、伝統的な装束を身にまとった参加者たちの行進が、歴史と宗教の雰囲気を堪能できる一大イベントとなっています。宝円寺へのアクセスは、金沢市内からも比較的アクセスが良好です。市内中心部からは車やバスを利用して、20分ほどで到着することができます。宝円寺はその歴史や宗教的な要素だけでなく、美しいまつりや年中行事などが組み合わさり、観光地としても魅力的です。境内には季節ごとに美しい自然や庭園が広がり、参拝客や散策客に心地よいひとときを提供しています。宝円寺は金沢市の歴史的な寺院であり、前田利家ゆかりの場所として親しまれています。歴史と宗教、美しいまつりなどが融合し、訪れる人々に静かなる時間と感動をもたらします。信仰の場としてだけでなく、観光地としてもぜひ訪れてみる価値がある場所だと思いますので一度足を運んでみては如何でしょうか。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 石川県には多くの神社仏閣があるのですが、その中でも金沢市内のひがし茶屋街の卯辰山寺院群にあるのがこの「寿経寺(じゅきょうじ)」です。以前、県外から友人が訪ねてきた時に、観光地であるひがし茶屋街を案内している時に、立ち寄ったお寺になります。地元では、七稲地蔵(なないねじぞう)の名で通っている神社で、その名の通り境内には稲を抱いた7体の地蔵が立っているの特徴で有名です。境内の金沢市教育委員会が掲げた案内看板には、このお地蔵様に付いての説明がなされていたのでご紹介します。今から約160年ほど前の安政5年(1858)、地震や長雨による凶作が続き米価が暴騰。飢えた民衆が当時町人入山禁止だった卯辰山に入り込み、米が高くて食べられないと直訴したいわゆる「卯辰山泣き一揆」が起こったとの事です。7体の地蔵は、この一揆で処刑された首謀者7人を供養のために祭ったものであるそうです。普通に散策していると分からないままに通り過ぎそうな寺院群ですが、しっかりの拝観することで、悲しい発見ではありますが、地元の者として感慨深く感じました。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 先日、東京から大学時代の友人が出張で金沢に来るという事で、一緒に観光で訪れた資料館を紹介します。金沢市の中心に位置する前田土佐守家資料館は、日本の歴史と文化を伝える重要な施設の一つです。この資料館は、加賀藩の歴史や前田家に関する貴重な展示物を収蔵しています。これから前田土佐守家資料館の展示物や概要、収蔵品、観光客への魅力、歴史的背景、金沢市や加賀藩の関連性、催事や講座についてご紹介したいと思います。資料館では加賀藩の武士の武具や、前田家の家宝として受け継がれた刀剣や、前田家に関する書画や史料、家訓、書簡などが展示されています。これらは加賀藩の歴史や前田家の家族関係を理解する上で重要な資料となっています。また、前田家の日常生活や文化に関する展示もあり、茶道具や調度品などが展示され、資料館自体が歴史的建造物として価値があり、その建築様式や歴史的背景も展示されています。前田土佐守家資料館は、観光客にとって魅力的なスポットの一つです。加賀藩の歴史や前田家に関心のある人々にとって、ここは必見の場所となっています。また、日本の武士道や武士文化に興味を持つ人々にとっても、貴重な情報源になると思います。前田土佐守家は、加賀藩の有力な家臣団の一つであり、金沢市を中心とする加賀藩の政治や文化に重要な影響を与えました。加賀藩は、戦国時代から江戸時代初期にかけて栄えた歴史的な藩であり、その文化や歴史は金沢市に色濃く残っています。前田土佐守家資料館では、定期的に催事や講座が開催されています。これには、加賀藩や前田家に関する特別展示や講演会、ワークショップなどが含まれます。これらの催事や講座は、一般市民や観光客が加賀藩や前田家の歴史をより深く理解し、その魅力に触れる機会を提供しています。前田土佐守家資料館は、日本の歴史と文化を伝える重要な施設であり、金沢市や加賀藩の歴史を理解する上で貴重な資料となっています。観光客や歴史愛好家にとって、訪れる価値のある場所です。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 金沢在住の私が愛してやまないお寺の一つがこの「雨宝院」であり非常に歴史のあるお寺になります。今住んでいる私の家から徒歩で5分と掛からないところにあるお寺で非常に馴染みがあります。場所は金沢市で一番の繁華街の片町から徒歩10分掛からない程で、金沢の中心を流れる犀川に架かる犀川大橋のたもとの川沿いにあります。このお寺が有名なのは、金沢の文豪である「室生犀星」のゆかりのお寺であるからです。室生犀星が幼少期から養子として育てられたのがこのお寺で、境内には犀星ゆかりの遺品や直筆の小説原稿、再生が書いたお寺宛ての手紙などの多くの品々が展示されています。私の子供たちが通っていた金沢市中心部の「中村町小学校」の校歌も室生犀星の作詞で地元石川県だけでも小学校、中学校、高校、大学を合わせると12校もの校歌を作詞しています。雨宝院の場所周辺は金沢では有名な「寺町(てらまち)寺院群」と呼ばれ、戦災にあっていないその街並みは、江戸時代の雰囲気が良く残っている地域となっています。室生犀星の数ある小説の中でも、この雨宝院がしばしば登場し、有名なところでは「性に目覚める頃」では、抹茶を好んだ養父の手伝いで、寺院の裏手から雑賀の水を汲みに行った事や、その川の水が清らかで澄んでいる事、鮎やウグイが泳ぐ姿など、雨宝院から見る犀川の美しさが非常に細やかに表現されています。境内には「まよい小石」という大きな石があり、この石にもたれたりするのを犀星は好んでいたと言う話も有名で、小説の中では『子供が道に迷ったりすると、この墓碑に祈願すれば、ひとりでに子供の迷っている町がわかる』石、として紹介されています。犀星の作品から大正期の金沢を思い起こす事は容易で、雨宝院はその中でも目立つ様な大きなお寺でもなく、犀川の川べりにひっそりと寄り添っている感じなのであるが、だからこそ心静かに昔を回想してゆっくりとした時間を過ごすには非常に良いお寺であると思います。近くには「室生犀星記念館」もあるので「雨宝院」と併せて訪れてみる事をお勧めします。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 金沢市にある西田家庭園「玉泉園」は、加賀藩の歴史を感じさせる美しい庭園で、観光客にとって魅力的なスポットです。先日久しぶりに東京から友人が遊びに来たので案内したところ、思いの外感動してくれたのでその歴史や見どころ、茶道文化などについて紹介したいと思います。玉泉園は、加賀藩の旧家である西田家の庭園として知られています。園内には、加賀藩第二代藩主前田利常によって造られたと伝えられる美しい池や庭園が広がっています。庭園の造りは、江戸時代の加賀藩の格式と美意識を反映しており、歴史的な価値が高いとされています。玉泉園の見どころの一つは、茶室や茶席があり、茶道文化を体験することができる点です。庭園内には、茶道の儀式を行うための茶室や、四季折々の景色を眺めながらお茶を楽しむことができる茶席が配置されています。訪れる人々は、茶道の精神や繊細な美意識を感じながら、庭園の中で心静かに過ごすことができます。季節によって、玉泉園の景色は異なる魅力があり、春には桜が咲き誇り、夏には緑の木々と水面が涼を呼び、秋には紅葉が美しい彩りを添え、冬には雪景色が庭園を幻想的に彩ります。四季折々の美しい風景を楽しむことができるため、一年を通じて多くの観光客が訪れるのも納得します。玉泉園への入園料は、大人700円、高校生600円、小中学生500円になり、菓子と抹茶付きの場合はそれぞれ1,000円プラスで楽しめるのも魅力の一つです。また、アクセスも便利であり、金沢市内からバスやタクシーを利用して比較的簡単に訪れることができます。金沢でも有名な兼六園からは徒歩で5分の距離にあるのでセットで散策するのもおすすめします。また、駐車場も完備されているため、車での訪問も可能です。西田家庭園「玉泉園」は、加賀藩の格式と歴史を感じさせる美しい庭園であり、茶道文化を体験する場としても知られ、四季折々の風景や季節の移り変わりを楽しむことができるため、多くの観光客にとって心に残る感動の場となっています。金沢にお越しの際は、是非観光スポットの一つとして散策することをおすすめいたします。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 石川県唯一のHISです。金沢の香林坊にあります。バス停は香林坊の日銀前とアトリオ前が近いです。車でお越しの際は近くのコインパーキングに停めていただくことになります。いつも入店したらすぐに声を掛けてもらえます。私は女性の方が担当でしたが、好感の持てる対応で是非またお願いしたいと思いました。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 石川県金沢市中心部長町にあります、『松の湯』さんをご紹介させていただきます。 『松の湯』さんは、金沢市繁華街 長町武家屋敷跡界隈のせせらぎ通りにあります。 金沢駅より北陸鉄道のバスにて、”金沢駅”より15分乗車し、”香林坊”にて下車をして徒歩5分ほどにあります。 駐車場は4台ほどあります。 お店専用駐車場が満車の場合は近隣のコインパーキングを利用してください。 『松の湯』さんの周辺の道は一方通行の道があるので注意してくださいね! 『松の湯』さんはとてもおしゃれなつくりをしています。 いまの『松の湯』さんがOpenしたのは、 2022年11月26日/いい風呂の日 もともとは、いまある長町武家屋敷跡界隈のせせらぎ通りに地元住人に親しまれ70年以上も続いた銭湯でした。 その銭湯が2020年に廃業。 今のオーナーさんの 「金沢で紡がれてきた銭湯文化を受け継ぎ、金沢の文化・歴史に触れて深めて楽しむ新たな場所を作りたい!」 の強い思いのもと復活オープンされました。 繁華街にある『松の湯』さん、先ほども書きましたが外装がとてもおしゃれです。 また復活オープンの際に内装にもこだわり、エントラスの壁や銭湯内の壁画にもオリジナルの「九谷焼」タイルが使用されていました。 私が伺ったときは、オープンから1年以上経っていましたがとても新しく、外人の観光客の方たちも多数利用されていました。 浴室内は残念ながら写真撮影NGなので投稿できませんでしたが、とても明るくおしゃれな「九谷焼」のタイル。 このタイルは全て金沢で活躍される若手からベテランの職人さんが作成されたようです。 素敵ですね! サウナ360円で利用できます。 タオル・バスタオル・サウナマット付きです。 銭湯内に「サウナ」「水風呂」「外気浴テラス」が完備されてます。 水風呂の苦手な方も外が涼しいときは「外気浴テラス」をゆっくり利用。 何度も往復してゆっくり体を休めることができますよ。 とてもおしゃれで、ゆっくり楽しめる空間。 また利用したいと思います。 ありがとうございました。
-
- 投稿ユーザーからの口コミ
- 金沢市東山に位置する安江金箔工芸館は、金沢の歴史と伝統的な工芸品である金箔をテーマにした博物館です。この地域は金沢の観光の中心地の一つであり、その文化的な重要性は大きいです。館自体も金箔を扱う工芸品を中心に収集・展示しており、その美しさと技術の高さには定評があります。館内には数々の展示物があり、その中には金箔を使った絵画や工芸品、さらには歴史的な文献や道具なども含まれています。訪れる人々は、金箔がどのようにして作られ、どのようにして使用されてきたかを学ぶことができます。展示されている作品は、その精巧さと美しさで訪れる者を魅了し、多くの人々に癒しと感動を提供しています。 特に、金箔工芸はその繊細さと高度な技術で知られています。金箔は紙の上に施されたり、陶器や木工品に貼り付けられたりすることで、美しい装飾や耐久性を提供します。これらの技術は数世紀にわたって受け継がれ、現代でもなお尊重されています。安江金箔工芸館では定期的に展覧会やイベントも開催されており、地域の芸術家や工芸家が新しい作品を発表したり、特定のテーマに焦点を当てたりしています。これらのイベントは、訪れる人々に新たな発見と体験を提供し、地域コミュニティの文化的な交流を促進しています。また、館内には図書室や資料室もあり、より詳細な情報を求める訪問者にとって貴重なリソースとなっています。ここでは金箔に関する文学や歴史、さらには伝統工芸技術について深く学ぶことができます。金沢を訪れた際には、この館を訪れて金箔の魅力に触れ、その芸術の奥深さを感じてみてください。開館時間は午前9時30分〜午後5時で入館は4時30分迄となっています。定休日は毎週火曜日で祝日の場合は翌平日が休館になり、年末年始は12月29日〜1月3日が休館との事です。観覧料金は一般は310円、団体で20姪以上では260円、65歳以上は210円で祝日は無料です。また高校生以下は無料なのも良心的です。このように、「金沢市立安江金箔工芸館」は観光客にとっての見逃せないスポットであり、その美しさと歴史的な価値は、訪れる人々に長く愛され続けています。
ホームメイト・リサーチに
口コミ/写真/動画を投稿しよう!
「口コミ/写真/動画」を投稿するには、ホームメイト・リサーチの「投稿ユーザー」に登録・ログインしてください。
Googleアカウントで簡単に最も安全な方法で登録・ログインができます。

ゲストさん
- ゲストさんの投稿数
-
今月の投稿数 ―施設
- 累計投稿数
-
詳細情報
―件
口コミ
―件
写真
―枚
動画
―本